一度くらいは耳にしたことはあるだろうか
雲海に浮かぶ天空の城。
正確には石垣が残る城跡だが、その幻想的な姿は
兵庫県内でも指折りの名所となっている。
その人気は姫路城にも勝るとも劣らない。
しかし、そんな神秘の光景がいつでも見られるというわけではない。
果たして、天空の城は姿を現してくれるのだろうか。
Text:Ryo Kawakami(YAMAKO)
Photo:Masahiro Kojima

ぬかるんだ地面は滑りやすいため、慎重に進んで行く。
まだ陽が昇る前の薄暗い山道を登るのは他でもない。雲海に浮かぶ天空の城「竹田城跡」を見るためだ。城跡の南東に位置するこの立雲峡は、雲海に浮かぶ竹田城跡が見られる絶景ポイントとして知られている。まだ眠い体に鞭を打ち、肌寒い気温のなか期待に胸を膨らませ歩いて行く。お世辞にも整備されているとは言い難い山道は、昨日降った雨でぬかるんだ地面が行く手を阻んでいた。まるで絶景への意気を試されているようだった。

びっしりと苔が付いた岩がゴロゴロ転がっている。

進めば進むほど期待と不安は高まってくる。それもそのはず、雲海はいつでも見られるというわけではない。良く晴れた風の弱い日という天候に加え、日中との寒暖差が10度以上なければならないという条件があるのだ。この日の天候は曇り。あいにく日中との寒暖差もさほどなく、条件的にはかなり不利な状況であることは理解しつつも、「見られるかもしれない」という微かな希望を持って歩みを進めていた。道中、小さな祠が目に留まった。ここを通る誰もがしてきたであろう、手を合わせ雲海が現れるよう願いを込めて強く祈った。

小さな祠は雲海を求む旅人たちの心の拠り所だ。

地上と空を隔てる雲海はやがて消えてしまう。儚い夢幻の光景を目に焼き付ける。
心臓破りの坂を越えると人の姿が見えて来た。ついに目的地である第一展望台に到着したのだ。そして同時に目に飛び込んできたのは、祈りが届いたのだろうか、紛れも無く雄大な雲海に浮かぶ天空の城だった。ここまでの苦労が一気に吹き飛ぶような大絶景が目の前に広がっていた。雲海は静かに形を変えながら幾度も竹田城跡を包み込んでいく。一瞬たりとも目が離せない。その神秘的な姿に、ここにいる誰もが息を呑んでいた。それを象徴するように誰も言葉を発さず、ただカメラのシャッターを切る音だけが響いている。雲海はAM8:00頃まで見られたがそれまでこの山を降りる者は一人もいなかった。
竹田城跡には2つの顔がある。1つは先述の「天空の城」として。そしてもう1つは「日本のマチュピチュ」である。現在も残された石垣の姿がペルーのマチュピチュに似ていることが所以だが、日本の山城として、ここまで遺構が残っているのは極めて稀なケースだそうだ。今度はその城跡に足を踏み入れるため、山頂に竹田城跡がある古城山を登って行く。もう一つの顔はすぐそこにまで迫っていた。 ※2016年2月末まで冬期閉山予定

遠くに見ていた城跡に、いよいよ足を踏み入れる。


圧倒的な光景だった。確かに城はない。しかし残された石垣がこれほどまでの存在感を放っていようとは予想だにしていなかった。現代に残された石垣たちはそれぞれの積み上げられた場所から微動だにしない。与えられた責務を全うする当時の威容をそのままに誇る姿は、まるで現在も石垣の上に城を支えているかのように見えるほどだ。現存する山城としては日本最大級という広大な敷地の天守台からは、かつて城下町があった町並みや円山川まで見渡せる。城主たちが眺めてきたであろう、360度絶景に囲まれた大パノラマが広がっていた。
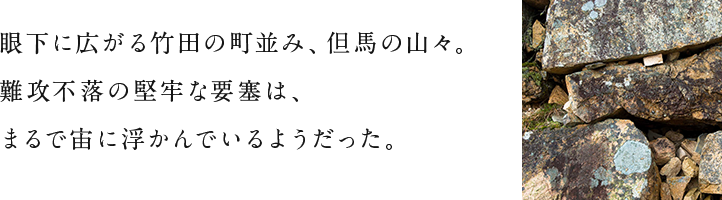

険しい地形にありながら、曲輪のすべてを石垣で取り囲んだ総石垣の城郭。
竹田城は但馬の守護大名、山名宗全が播磨侵略のため13年を費やして築いたと伝えられている。羽柴秀吉の2度の但馬征伐で家臣の赤松広秀が城主となり、豪壮な石垣積みの城郭を築いたという。石垣の積み方は織田信長の安土城と同じ「穴太積み」という技術が用いられている。石材は現地や山麓付近から集めたものと考えられ、大きいものは5トンにも及ぶとか。築城に関しては不明な点も多いが、山の地形を防御に活用するなど軍略に堪能な人の手による構築と言える。廃城から400年を経た現在でも、城主の帰りを待っているようにも感じられた。
山の麓はかつての城下町の面影が見られる趣きのある風景が続いている。周辺には散策の疲れを癒す食事処が点在し「旧木村酒造場 EN」もそのひとつ。400年ものあいだ、竹田の地で酒造りに情熱を注いできた老舗酒造場を改築したレストラン・カフェ、さらには宿泊所等を併設する複合施設で、地元の食材を活かした料理を味わえるのもうれしいところ。ここからは山頂の竹田城跡を下から眺めることもできて、当時の庶民も同じ風景を眺めていたのかもしれない。

レストランの2階には隠れ家的なカフェが。

地元の食材を使用した旬の料理が味わえる。

かつての酒造場の一部も展示されている。

明治期に建てられた建物をリノベート。


-

400年の時を越えて、今にその姿を残す石垣。
-

竹田の町並みと、但馬の山々を一望できる。
-

雲海発生時、立雲峡の山道は霧に包まれ幻想な雰囲気に。
-

なだらかな道や、勾配のきつい道を越えて展望台を目指す。
-

旧木村酒造 ENのカフェからはレトロな景色が。
-

かつての城下町を彷彿させるような風情ある町並み。
書寫山圓教寺(しょしゃざんえんぎょうじ)は
「西の比叡山」と呼ばれるほど寺格の高い、
西国三十三所のうち最大規模の寺院だ。
比叡山、大山とともに天台宗の三大道場と並び称された古刹で
そこには自分を見つめ直す、非日常が広がっている。
荘厳な空気の中、坐禅や写経を通して
新たな自分を見出すことはできるのだろうか。
Text:Ryo Kawakami(YAMAKO)
Photo:Masahiro Kojima

ロープウェイなら山頂までわずか4分。姫路市内も一望できる。
書寫山圓教寺は標高371mの山頂に建っている。六本もの参道から山上へ向かうことができ、その風景も様々だ。足腰に自信がなくてもロープウェイを利用して一気に御堂付近まで行くこともできる。そこからまた分かれる参道が最大の選択の場だ。木漏れ日の差し込む美しい馬車道か、あるいは参道に沿った33体の観音様の待つ坂道か。地図を見ながら進む道を選ぶのは、書寫山巡りの楽しみ方でもあるのだ。
森を抜けると、突如荘厳な建物が姿を現した。西国霊場の第27番札所として知られる摩尼殿(まにでん)だ。足場は京都の清水寺と同じ舞台造りが用いられており、石段の先に見える御堂はまさに壮観だ。1921年(大正10年)に火災に遭ったため、現存のものは1933年(昭和8年)に再建されたもの。御堂前の湯屋橋付近には書寫山で修行をしたと伝えられる弁慶が、お手玉代わりに投げたと伝えられる大きな石も置かれている。下界とは異なる空気を味わいながら、この橋のたもとにある、はづき茶屋で一息つくのもまた風情である。

摩尼殿の舞台からは美しい自然と参道が見渡せる。

崖の上の建物を長い柱と貫で床下を固定する「懸造り(かけづくり)」。


神聖な空気に包まれた堂内。重厚な扉の向こうには御本尊が。
摩尼殿の中は静寂に満ちていた。張りつめた空気が立ちこめ、否が応でも緊張させられる。なにせ、ここには御本尊である如意輪観音のほか、国指定の重要文化財である四天王立像も安置されている神聖な場所。秘仏であるため普段目にすることはできないが特別に開帳される時期もあるのだとか。陽の光も届かない内陣はまさに圓教寺の聖域なのである。
実は摩尼殿は本堂ではない。杉木立の坂を抜けると大きな三つの堂がコの字型に並んだ広場に出る。左から阿弥陀仏の名を唱え本尊を回る修行場「常行堂」。中央に見えるのは、元々修行僧の寝食のために建てられたという「食堂(じきどう)」。そして右に見えるのが圓教寺の本堂に当たる「大講堂」である。映画や大河ドラマにも使用された場所とあって、この一角だけは時が止まったかのような別次元の感覚を覚える。室町時代から書寫山を見守ってきた御堂が、当時の空気を現代に伝えているのだろうか。

広い敷地に三つの堂が顔を寄せ合うように建てられている。


天台宗では坐禅のことを「止観(しかん)」と呼ぶ。言わずもがな、僧侶たちの修行の一つ。厳かな空気の中、坐り方や呼吸法などの指導を受け、しばし精神統一に集中する。呼吸を一つ、また一つ。自分を見つめ直し、日常の不安や苛立ちを解き放っていく。いつの間にか寒さを忘れ、静寂のなか鳥のさえずりだけが響いていた。一時、意識が日常に戻ると僧侶は目の前で立ち止まった。そして禅杖(ぜんじょう)と呼ばれる棒で背中を叩いたのだ。全てお見通しというわけか。実はこれは罰ではない。修行者の精神を整え、正しく禅を組むための“励ましの意”だという。

坐禅(止観)を体験したのは先述の修行場である「常行堂」。内部に入るや否や、安置されている阿弥陀如来像の威風堂々たる佇まいに圧倒されたが、今度はまた別格の雰囲気が漂う「食堂」で写経を体験した。広い堂内の解放的な空間で一文字、また一文字書き写していく。写経は坐禅と並ぶ代表的な修行の一つだが、元々は印刷の技術がない時代の文字写しの業であったという。雑念を振り払い、ただ一心に筆を進めているといつの間にか無心になっている自分に気付かされた。

普段見慣れない漢字に始めは意識するものの、徐々に無へと近づいていく。

僧侶は圓教寺の歴史など、たくさんの話を聞かせてくれた。
圓教寺は姫路市内の小学校の林間学校に使われるため、昔から市内の子どもたちは三つの堂の広場や食堂を、校庭や廊下のように駆け回るのだそうだ。一見厳格な境内の雰囲気に萎縮しそうだが、修行の場を書寫山に切り開いた「性空上人(しょうくうしょうにん)」は常に慎ましさを望んでいたという。そんな思いからか寺格はあれど、多くの人々に親しまれる場所になったという。権勢や栄華を避け、ひたすら信仰と修行の道に生きた「性空上人」。その人柄にこそ、恩徳を感じることができるのではないだろうか。


-

修行の場「常行堂」に祀られる阿弥陀如来像。
-

森の間から神々しい光が差し込む圓教寺。
-

書寫山は季節毎に趣きの異なる表情を見せる。
-

湯屋橋を越えると、石段の先に摩尼殿が佇んでいる。
-

写経の正しいやり方を丁寧に指導していただいた。
-

随所に美しい建築が施されている。







































